読んだ本の数:2
読んだページ数:160
ナイス数:1
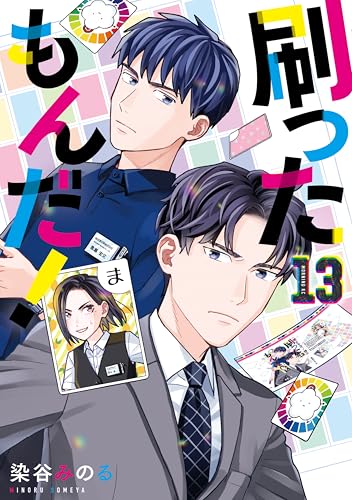 ]]>
]]>
10月いっぱいで1つレギュラーの仕事が切られ、少し時間のゆとりができたので、以前から考えていた自分のメディアを作ってみることにした。
記と憶 Ki to Oku
https://ki-to-oku.ghost.io/
テーマは、「記憶」と「記録」。このテーマを選んだ理由はいくつかある。
自分がこれまで触れてきた物語や創作物の中で、特に心に残っている作品で「記憶」が鍵になっていると気づいたのが最初。忘却、喪失、改ざん、再生など、記憶にまつわるテーマに「なぜ自分は、これほど心を動かされるのか」という問いがあった。
あと、メディアのテーマは大きすぎても小さすぎてもいけない。基本的に一人で運営するつもりなので、あまり広げすぎると手に負えないし、内容も散漫になる。狭くしすぎると興味を持つ人が限定されてしまうし、ネタも尽きやすく、おそらく自分も飽きてしまいそう。
「記憶」と「記録」という軸であれば、普遍的な問いを扱えるだけでなく、これまで仕事で関わってきたテクノロジー分野も範疇に入ります。
半導体メモリやデータストレージといった物理的な記録から、AI、量子コンピュータ、ブロックチェーン、BMI(ブレイン・マシン・インターフェース)、さらには神経科学や心理学、公文書管理やその改ざんといった政治的・倫理的な問題、デジタルアーカイブの永続性といった社会課題まで、多方面の話題を扱える。
これまでは「依頼を受けて書く仕事」が中心だったが、自分の「母艦」となるメディアを持つことで、すべての仕事に良い影響が生まれそうな予感がある。一つのテーマを定点観測することで、世の中の見え方が変わり、インプットの質も変わる。この場所を少しずつ育てるために、普段の仕事の効率を高め、隙間時間を大切にしようという意識も生まれる。
プラットフォームには「Ghost」を選んだ。理由はGhost自体がActivityPubに対応していること。2年ほど前からSNSはMastodonをメインとしてきて、Fediverse(分散型SNS)に好感を持っていたから。Ghostは日本語ユーザーがまだ少ないが、Fediverse連携の可能性を感じている。
生成AIをフル活用している。文章を書くことはもちろん、記事のネタや企画・構成についての相談、ロゴやプラットフォームのデザイン設定の相談、記事につける画像を生成するためのプロンプト作成など。英訳もしてもらっていて、Mediumに『記と憶 Ki to Oku Annex』として載せているので、よければ覗いてみてください。
ちなみに10月で切られた仕事がなぜか再開することになり、また少し忙しくなりそう。
]]>しばらくATOK Passport [ベーシック]を使っていたんだけど、[プレミアム]に統合されて税込330円から660円になるというので反射的に解約してしまった。
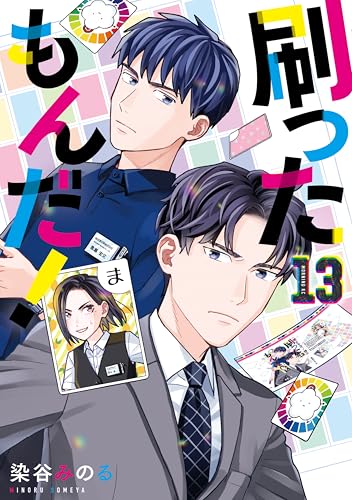 ]]>
]]>
だいぶ前に2chまとめか洒落怖で読んで印象に残っていた話があったのだけど、また読もうと思って探しても見つけられなかった。でも昨晩たまたま寝付き用に聞いていたYouTubeの朗読チャンネルでこの話が流れてきて「これだーー!」ってなった。ここ数年たまに思い出しては見つからずもやもやしていたので超スッキリ。
【朗読】島根県にある閉鎖された村 - YouTube
東京大学 学内広報 NO.1599 淡青評論 第1184回「AIを引っ提げてやってきた大学院生」
いい文章だし、お手本にしたい良い文章。
過不足がなく、筆者が率直にたまげたり恐れたりしていて、院生の顔や佇まいが目に浮かぶようだ。
]]>




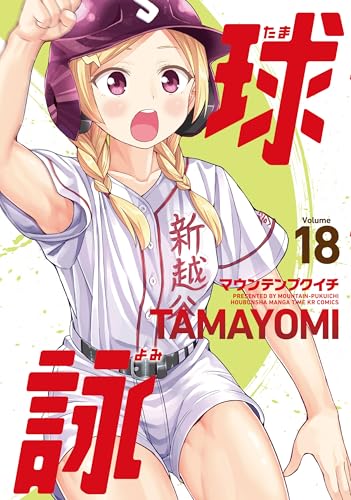




ジャケ買いした

ここ数カ月、Netflixで日本のテレビドラマをいくつか観た。うちのテレビは10年以上前に捨てたし、その前からドラマはあまり観てこなかったので久しぶりだ。
観たのは「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」「イノセンス 冤罪弁護士」「アバランチ」。出演者の内田有紀や瀬戸朝香、吉田栄作、仙道敦子、ともさかりえ、酒井美紀、木村佳乃、国生さゆり、思い出せるのはこの辺りかな。若い頃のキラキラしたイメージしかない人ばかりだけど、みんないい歳になっていい演技をしていて、時の流れを感じたし、同じ時間を生きてきたんだなぁと感慨深い。
]]>




 ]]>
]]>
SHIBUYA DIVEで行われた、nano.RIPE DEBUT 15th ANNIVERSARY ONEMAN 「みずのもんしょう」に行ってきた。3週間くらい前にチケットを買ったものの、正直行こうかどうか迷ってた。直前に雨も降ってくるし。だけど、行っておいてホントよかった。
nano.RIPEのワンマンは今回でたぶん4回目かな。あとはアニメ関係のフェスとか、深窓音楽演奏会で1回ずつのはず。「シングル全曲披露」を謳っていて盛り上がらないわけがないライブだったけど、きみコさん、今まで観た中でも一番楽しそうにしていたな。およそ2時間半たっぷり楽しんだ。きみコさんの、うたっていないとき(というか間奏のとき)、横に大きめに揺れる独特なステップを踏みながらギターを弾くんです。それが美しくて眺めるのが好きなんだよね。nano.RIPEのライブに行く理由の大きなものの1つ。
nano.RIPEを初めて知ったのは、のんのんびよりのOPだったので、「なないろびより」と「こだまことだま」が聴けるとうれしい。あとはやはりタオル回し曲「リアルワールド」。最近の曲はあまり聴いていなかったので、普段から聴いておこうと思う。
今日のドラムは初めて見た人だったけど、好きなドラムだった。ステージでは「ショート」と呼ばれていて気になったのだけど、XでライブのことをつぶやいたらLikeを付けてくれた。三隅憧人(みすみしょうと)さんという方だった。いろんなバンドで叩いているようで、さっそくXでフォローした。

(10/4追記)当日の模様がYouTubeで公開。
]]>内面自己の反省は常に秋の霜のように冷厳に行ひなさい。自分のことは寛大であつては、人を尊重し得ない訳で、結局苦境に堕ちる。
たしか八幡山に住んでいた頃だったと思うからたぶん20年くらい前、正月に神社で引いたおみくじに書いてあった言葉がとても気に入っている。いつもこの通りできているとは全く思わないが、心がけるようにしたい。
]]>




 ]]>
]]>




 ]]>
]]>








2006年頃かな。台所でタコを切っていると桐が寄ってきたところの写真。八幡山に住んでいた頃だ。誰が撮ってくれたんだっけ、これ。
]]>

任意のURLが設定できないため、タイトルに入った英数字はそのまま、かなはローマ字、漢字は中国語の読みという妙な感じになってしまう。今までは最初にアルファベットだけのタイトルを入れてPublishして思い通りのURLを作成し、それから再度タイトルに日本語を入れて保存するというようにしていたが、まあ馬鹿馬鹿しいのでやめにする。
]]>




4月の読書メーター
読んだ本の数:1
読んだページ数:288
ナイス数:0
カウンターエリート (文春新書 1492)の感想
この社会の何をどういうふうに変えたいか、をより大局的な視点で分かっている人たちこそが世界を形作っていくのだな、と思った。それと、呉越同舟?同床異夢?考えが合わない人たちとどう組んで目的を果たすか、現在進行系のお話。その意味で、宣伝文句として石丸や斎藤の名前を出しているのだと思うけど、次元が違う。かれらはカウンターエリートではない。
読了日:04月21日 著者:石田 健
読書メーター

柏のキネマ旬報シアターで映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』を観てきた。「面白いらしい」という以外の事前情報は全くない状態で観たおかげか、かなり楽しめた。見せたいものがはっきりしている映画はいいね。2時間超えだったし、肩に力が入って疲れた…。あとやっぱり刃物は苦手。
CGを使ったアクションは迫力があるし、CGでないと作れないシーンもあるので使うのはいいんだけど、やっぱりどこか身体性のリアリティみたいなものは失われて、そのぶん旧い香港映画っぽさは薄れていたように思う。ただ、それを補って余りあるスペクタクルは十分満足できるものだった。そして龍捲風がかっこよすぎた。観てる途中で何度も煙草が吸いたくなった。
クレジットで日本人の名前が気になった。音楽の川井憲次氏と、アクション監督の谷垣健治氏。谷垣健治氏のことは知らなかったのだけど、メイキング動画観たら広東語を普通に喋っていて、この作品の肝とも言える部分を作ったのだと思うと「すごい」の一言しかない。
]]>





意外とまだ咲いてた。桜の名所もいいけどだいたい人が多いか酒臭いので、街なかで咲いている桜のほうが好き。
]]>「一文の文字数」と「句読点までの文字数」はいまいちピンとこない数字。



